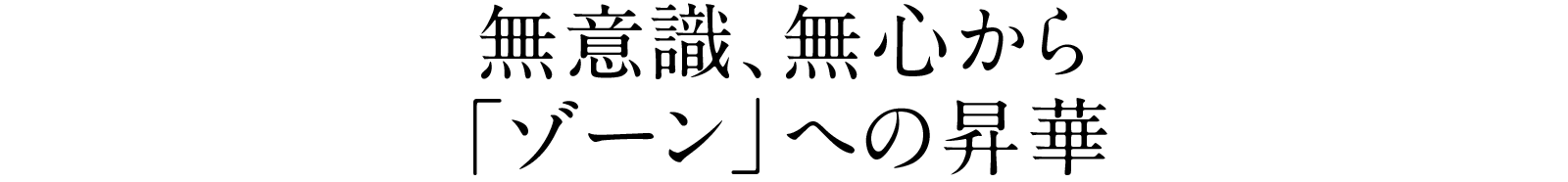本学の特別招聘教授で料理研究家の土井善晴先生と、2012年のソフトボール世界選手権に日本代表として出場した人間生活学部健康栄養学科助教の相馬満利先生の対談を全6回にわたって紹介します。今回、初めての対面となったお2人の座談会。土井先生の「なぜ人間は動くの?」という根源的な疑問からスタートした対談は、スポーツと料理の意外な共通点へと発展していきました。
目次
- 第1回
- スポーツを楽しむについて
- 第2回
- 経験の無限の蓄積が、偶然をものにする力(セレンディピティ)を呼び込む
- 第3回
- 「一生懸命」のプロセスが、成長につながる
- 第4回
- 無意識、無心から「ゾーン」への昇華
- 第5回
- 「他者を思うこと」で、力を発揮できる
- 第6回
- スポーツと料理の“道具”を使うコツとは?
土井 ところで、相馬先生はホームランって打ったことはありますか?打ったらやっぱり気持ちがいいものなんですか?
相馬 はい、あります。私はホームランバッターではなくて、どちらかというとヒットでつなぐタイプですが、打ったことはあります。やっぱりすごく気持ちがいいですね。
土井 きっとすごくうれしいですよね。私も軟式野球をやるのですが、1回も打ったことないんです。軟式の打球ってなかなか上がらないからホームランって難しい。一回、打ってみたいなぁ。
相馬 すごく調子がいいときは、何も考えないでたぶん目をつむっていても打てるんです。
土井 え? 目をつむっても?
相馬 自分のゾーンに入っていると、自分のバットの軌道もタイミングも多分ばっちり合っているので、打てる自信があるんです。
土井 それはすごい!
相馬 そういう経験はあります。そのときは、どんなピッチャーが来ても打てるなと思いました。
土井 ゾーンということは、「頭で考えていない」という状況ですよね。そのゾーンに入っているときに、客観的に見ている自分がいませんか?

相馬 そうですね。俯瞰の目のように、自分で自分を見ていることがありますね。
土井 そうそう、自分ってすごいなと感動するような。
相馬 そうです。なんと言えばいいでしょう。オーラを感じるというか、「自分って最強だ!」と感じるような。
土井 私も料理で、ゾーンに入ったような経験があります。トロ箱いっぱいのキスをね、きれいに水洗いしてさばかなければならなかったんですけど、ものすごく忙しいときで、ものすごく一生懸命やったんですよ。そうしたら、ゾーンに入ったというのかな。自分を俯瞰するような感覚で、自分の手が見えないくらい速く動いているのを見て、すごく感動した経験があるんですよ。外国で料理をしているときにも、同じような心境になって、とても時間内には終わらないと思った作業がきちんと間に合ったという経験があるんです。
相馬 やはり、お料理もゾーンに入るということがあるのですね。
土井 自分で自分に驚くというね。それはもう感動的でした。そこにはきっと、頭が整理されていて手が動く、体が勝手に動いているという状況があるのだなと感じますね。
相馬 分かります。体が勝手に動く感覚ですよね。それは成功体験として自分のなかに残っていくので、そのときの自分を目指して、また頑張るようになったりしますね。
土井 そういうゾーンに入るような経験というのは誰にでも訪れるものではなくて、一生懸命に積み重ねてきたからこそ生じる現象なのではないでしょうか。一生懸命にやった自分へのご褒美みたいに、ときどき出てくるのかも分かりませんね。努力の向こう側にある、そのすごい境地をちらっと見せてくれているのかもしれませんね。
相馬 そうですね。ゾーンに入るというのは、集中力が極限まで研ぎ澄まされ、競技に没頭している状態ですよね。そうなるためには、はっきりとした目的意識を持ち、努力し続けることが不可欠だと言われているので、一生懸命取り組むという過程なしには起こりえないことですね。高校生のとき、全国大会の準決勝の前夜、亡くなった父が夢に出てきて、バットの握り方を変えるよう教えてくれました。試合当日、2点ビハインドで迎えた打席で、バットの握り方を変え、逆転スリーベースヒットを打つことができました。今振り返ると、これも一種のゾーンなのかなと感じています。
土井 それはすごい! ゾーンに入る状態というのは、つまりは無心の状態ですよね。ゾーンにいつでも入れるわけではありませんが、その前提となるような心の状態を生み出すには、私は、無心の状態になる、ゼロというコンディションが大事だと思っています。
そういう状態に持って行く一つの手段になっていると思いますが、私は、テレビでも講演会でも、いつも何を話すか分からないんです。資料はちゃんと用意していきますが、今日皆さんと初めて会った自分がどんな反応をするのかを見たいから、とかいろいろ言いながら始めるんです。そうすると、そのときだけの話ができる。予定した通りやらないんですよ。
相馬 なるほど。私も授業をするときに、生徒の様子を見て、敢えて用意してきた資料を使わないこともあります。専門的な知識を教える授業はきちんと予定通り行いますが、実技を伴う授業のときは、感覚の方が大事だと思っていて、その感覚に頼って授業を進めています。
土井 そうそう、その「感覚」って大事ですよね。自分で料理する楽しさは、自分の感覚を使う楽しさなんです。だからレシピに頼るのではなく、素材を見て、今日はどうかな?と感じて調理するのが楽しい。
相馬 素材を見て感じる・・・。なかなかその境地までいくのは難しそうな・・・。
土井 素材があったら、煮るか蒸すか焼くか、どれにしようかと考える。味付けとか工夫とか、そういう複雑なことは置いておいて、まずはそれだけでいいんです。その後の工夫はいくらでもできるから。素材と対話して、焼こうかな?蒸すのがいいかな?と対話することでいいんですよ。イモを煮たら、ちょうどいい具合に煮上がって、イモがご機嫌にしてるなと感じたり。夏やったら、ナスが瑞々しい。でも秋になると少し水分が抜けて種が大きくなり堅くなる。だから料理の仕方も変わってくるとかね。

相馬 すごい。そんなことを考えたことがなかったです。
土井 素材を見て、「ええ顔してるな」とか、「美しいな」って。それはパッと出会いだから、そのときの感性やね。素材が、自分の心を無にしてくれるんですよ。
相馬 料理をするときに素材と対話をしたことがないです。そもそも心が入っていなかったかもしれません・・・。
土井 いやいや、きっとそういう体験は料理以外でも、日常にあることだと思いますよ。外に出た瞬間、いい天気やなとか、いい風が吹いてきたなと感じるでしょう。それは自分が無になっているのだと思います。無になっているから、風や空の様子を受け取り、素直に感じることができる。それって気持ちがいいものでしょう。その気持ち良さの中に入っていくような感覚が、料理の入り口にあるんですよ。素材を見たら、きれいだな、おいしそうだなと思うことがすごく重要だなと思います。
相馬 なるほど。そういう意味で言うと、試合でグラウンドに入るときに、土の硬さやスタンドの向き、風向きなどの雰囲気を感じ取って、「ここはやりやすそうだな」などと感じることがありますね。
土井 野球やソフトボールの試合では、グラウンドを整備して、始まるときにサイレンが鳴ったり、選手が全員整列したりするじゃないですか。あの瞬間はやはり「無」ですよね。その状態というのは、何かその場の雰囲気が初期化、デフォルトされているんだと思います。それは、スポーツでも料理でも、いいスタートが切れるようにするためにすごく大事だということだと思います。
料理は基本的には一人で素材と相対するところがありますが、ソフトボールは団体競技なので、チームメイトとの関係性、つまり他者との関係性ということにもとっても興味があります。そのへんのお話も聞かせていただけますか。
(次回へつづきます)
2022.11.25
PROFILE

土井善晴(どい・よしはる)先生プロフィール
1957年大阪府生まれ。スイス、フランスでフランス料理を学び、帰国後、大阪の「味吉兆」で日本料理を修業。土井勝料理学校講師を経て、1992年に「おいしいもの研究所」を設立。本学では特別招聘教授として教鞭を執る。東京大学先端科学技術研究センター客員研究員。『一汁一菜でよいという提案』(新潮文庫)、『一汁一菜でよいと至るまで』(新潮新書)、『料理と利他』(中島岳志共著・ミシマ社)など。

相馬満利(そうま・まり)先生プロフィール
1990年神奈川県出身。2012年、第13回世界女子ソフトボール選手権大会で大学生唯一の日本代表として出場。ポジションはショートで、上野由岐子投手らとともに42年ぶりにアメリカを倒し世界一となる。2013年、ルネサスエレクトロニクス株式会社(現:ビックカメラ)に入社し、日本代表としてアジア大会優勝と日本一を経験。現在、十文字学園女子大学 人間生活学部健康栄養学科助教。専門は、スポーツバイオメカニクス、形態測定学、トレーニング科学など。