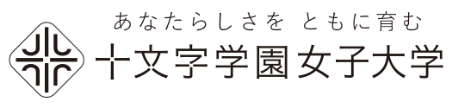社会情報デザイン学科の学生が「野寺町会・野寺自主防災会」(新座市)について現地調査を行いました

8月5日(火)に社会情報デザイン学科の授業「社会調査実習」の一環として、新座市の野寺町会・野寺自主防災会について現地調査を行いました。
当日は、野寺町会会長で野寺自主防災会会長の野島さま、町会員でにいざ歴史文化財研究会副会長の平田さまにご協力いただき、武野神社の湧水による弁天池、黒目川の水車跡や用水路跡を見学しました。
現地を歩きながら、武蔵野台地の地形的特徴や土地利用の歴史を学んだ後、自主防災会の活動についてインタビューを実施し、学生たちは、地域防災の共助の工夫や直面する課題について、直接学ぶ貴重な体験となりました。
当日は、野寺町会会長で野寺自主防災会会長の野島さま、町会員でにいざ歴史文化財研究会副会長の平田さまにご協力いただき、武野神社の湧水による弁天池、黒目川の水車跡や用水路跡を見学しました。
現地を歩きながら、武蔵野台地の地形的特徴や土地利用の歴史を学んだ後、自主防災会の活動についてインタビューを実施し、学生たちは、地域防災の共助の工夫や直面する課題について、直接学ぶ貴重な体験となりました。
参加した学生の感想
◆地域の水利の歴史を学ぶことは、気象変動でゲリラ豪雨が頻発する中、水害のリスク管理につながることがわかりました。ありがとうございました。(3年生)
◆事前に教室で、町会員の小清水さまから、八石小学校での防災訓練についてレクチャーを受けました。現地を歩いてみて、町会エリアの地歴を素材にした防災絵本があれば、子どもたちも楽しく防災を学べそうだと思いました。(3年生)
◆事前に教室で、町会員の小清水さまから、八石小学校での防災訓練についてレクチャーを受けました。現地を歩いてみて、町会エリアの地歴を素材にした防災絵本があれば、子どもたちも楽しく防災を学べそうだと思いました。(3年生)