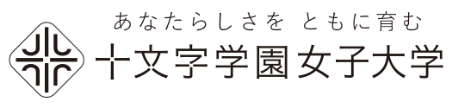10月4日(土)5日(日)で開催された特別支援教育実践研究学会で、本学科の学生がポスター発表を行いました

発表では、たくさんのご質問ご意見をいただき、今後の研究活動のはずみとなりました!
本学科の卒業生2名の口頭発表、ポスター発表もありました。
発表した学生の研究テーマは、主に以下の内容になります。
本学科の卒業生2名の口頭発表、ポスター発表もありました。
発表した学生の研究テーマは、主に以下の内容になります。
- 強度行動障害のある児童等の対応に関する研究
- 特別な支援を必要とする児童への教科指導上の手立ての効果の確認方法に関する一考察
- セサミストリート「ジュリア」に見る自閉症の障害特性と障害理解に関する一考察
- 文部科学省著作教科書星本さんすうの活用に関する一考察
- 地域の特別支援教育の推進・充実のための特別支援学校のセンター的機能の取り組みに関する一考察
- 知的障害の児童等における自立活動の指導に関する一考察
- 障害のある児童等の思考力・判断力・表現力等を育む授業づくりに関する一考察
強度行動障害のある児童等の対応に関する研究
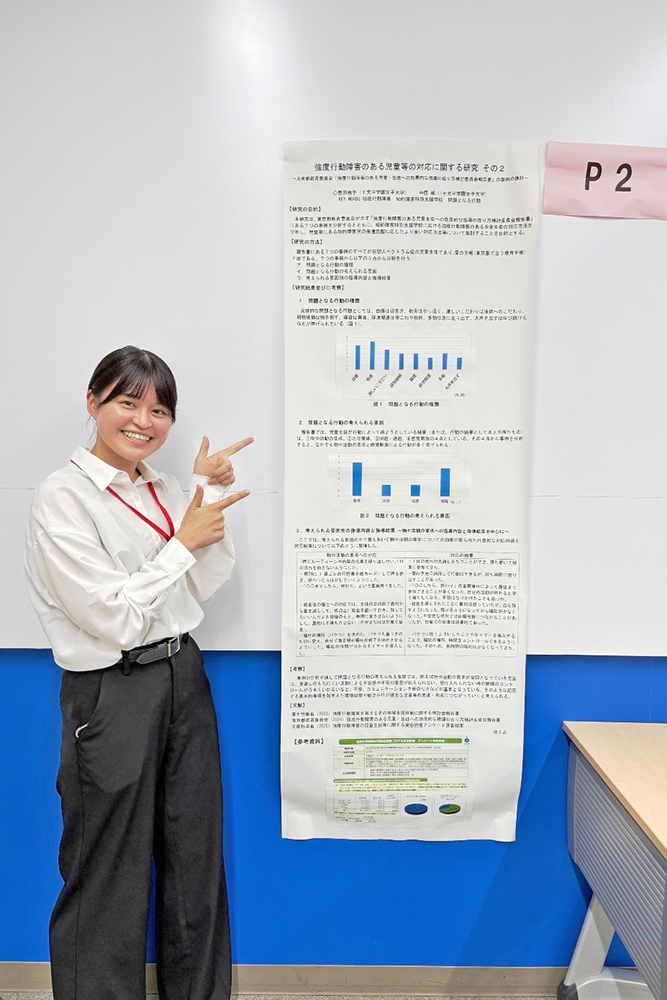
知的障害特別支援学校に在籍する強度行動障害のある児童生徒7名の事例を分析し、知的障害特別支援学校における強度行動障害のある児童生徒の対応方法を検討しました。そのことにより児童期にある知的障害のある児童生徒の発達段階に応じたより良い対応方法等について考察しました。
ポスター発表では、効果的な対応方法を中心にまとめ、紹介したのですが、うまくいかなかった対応も検討する必要があることや、問題の行動となる要因では「要求活動」が一番多い結果に対して、要求を上手に伝えられるようにするための指導を研究することで「研究に面白みが増すね」とのアドバイスをいただきました。
ポスター発表では、効果的な対応方法を中心にまとめ、紹介したのですが、うまくいかなかった対応も検討する必要があることや、問題の行動となる要因では「要求活動」が一番多い結果に対して、要求を上手に伝えられるようにするための指導を研究することで「研究に面白みが増すね」とのアドバイスをいただきました。
特別な支援を必要とする児童への教科指導上の手立ての効果の確認方法に関する一考察
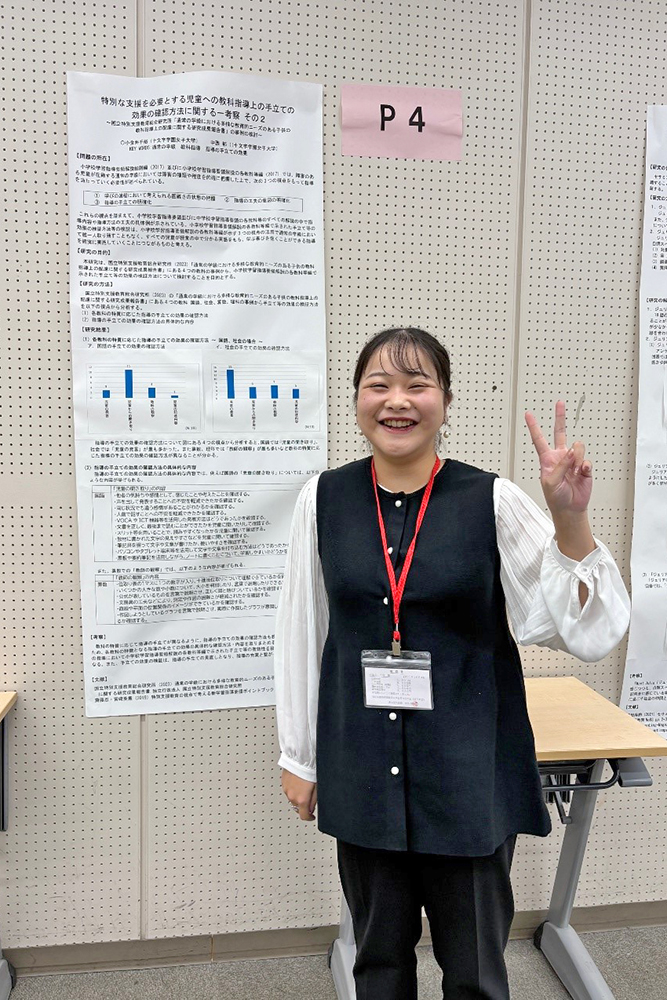
国立特別支援教育総合研究所(2023)「通常の学級における多様な教育的ニーズのある子供の教科指導上の配慮に関する研究成果報告書」にある4つの教科(国語、社会、算数、理科)の事例から、小学校学習指導要領解説の各教科等編で示された指導の手立て等(①学びの過程において考えられる困難さの状態の把握、②指導の工夫の意図の明確化、③指導の手立ての明確化)の効果を分析しました。
ポスター発表では、手立ての効果の分析は指導の手立ての見直しとなり、指導の充実と繋がっていくので、今回の研究の成果を小学校の教師として実践し、研究を実践的な研究としていくようにアドバイスをいただきました。
ポスター発表では、手立ての効果の分析は指導の手立ての見直しとなり、指導の充実と繋がっていくので、今回の研究の成果を小学校の教師として実践し、研究を実践的な研究としていくようにアドバイスをいただきました。
セサミストリート「ジュリア」に見る自閉症の障害特性と障害理解に関する一考察
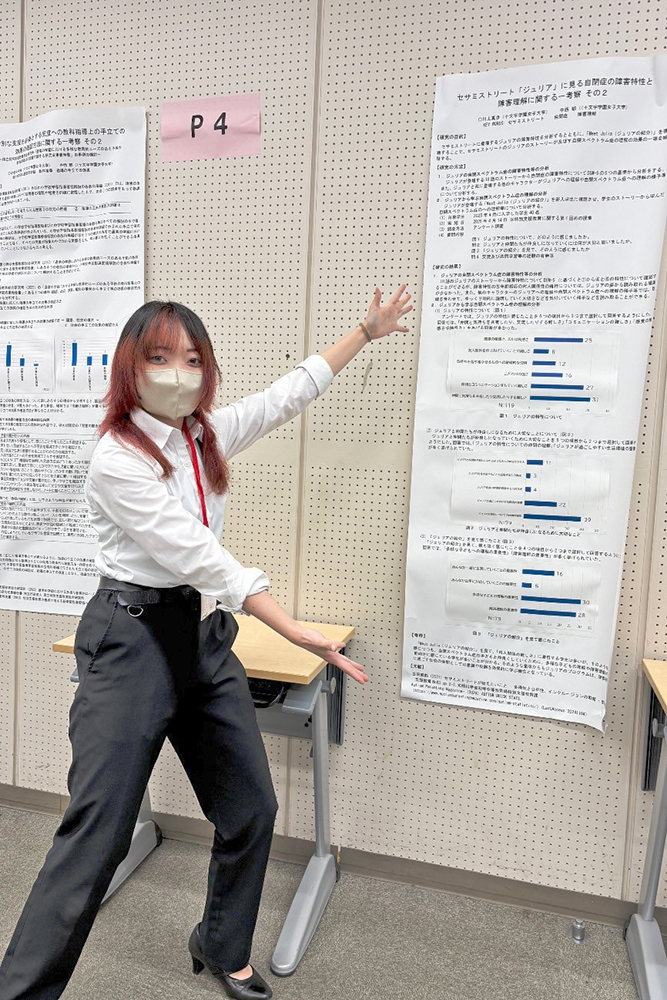
セサミストリートに登場するジュリアの障害特性をDSM-5の6つの基準から分析するとともに、本学児童教育学科1年生の学生に「Meet Julia(ジュリアの紹介)」を視聴することで、セサミストリートのジュリアのストーリーが及ぼす自閉スペクトラム症の理解の効果の一端を検証しました。
ポスター発表では、大変ユニークな研究であると評価をいただきました。ジュリアの研究と併せてアメリカにおけるセサミストリートの歴史や社会に果たしてきた効果や役割について研究すると深まりがある研究になるとアドバイスをいただきました。
ポスター発表では、大変ユニークな研究であると評価をいただきました。ジュリアの研究と併せてアメリカにおけるセサミストリートの歴史や社会に果たしてきた効果や役割について研究すると深まりがある研究になるとアドバイスをいただきました。
文部科学省著作教科書星本さんすうの活用に関する一考察
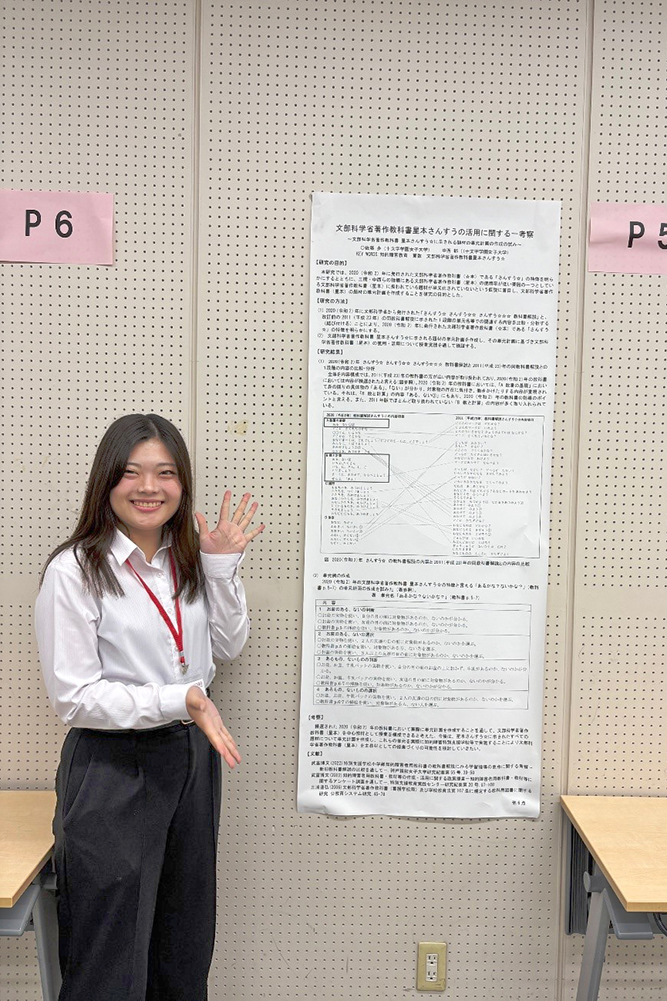
文部科学省著作教科書(星本)の使用率が低い要因の一つとして、文部科学省著作教科書(星本)の解説書に扱われている題材が単元化されていないという仮説のもと、文部科学省著作教科書(星本)の題材の単元計画の作成と実践の意義について発表しました。
ポスター発表では、文部科学省著作教科書(星本)の使用に関心がある多くの先生方からご意見をいただきました。特に星本が使用されていない現状について特別支援学校等の現場の先生方から伺うことができたことや、単元計画があれば授業の中で星本が使いやすくなるとのご意見もいただき研究を進めていく励みとなりました。
ポスター発表では、文部科学省著作教科書(星本)の使用に関心がある多くの先生方からご意見をいただきました。特に星本が使用されていない現状について特別支援学校等の現場の先生方から伺うことができたことや、単元計画があれば授業の中で星本が使いやすくなるとのご意見もいただき研究を進めていく励みとなりました。
地域の特別支援教育の推進・充実のための特別支援学校のセンター的機能の取り組みに関する一考察
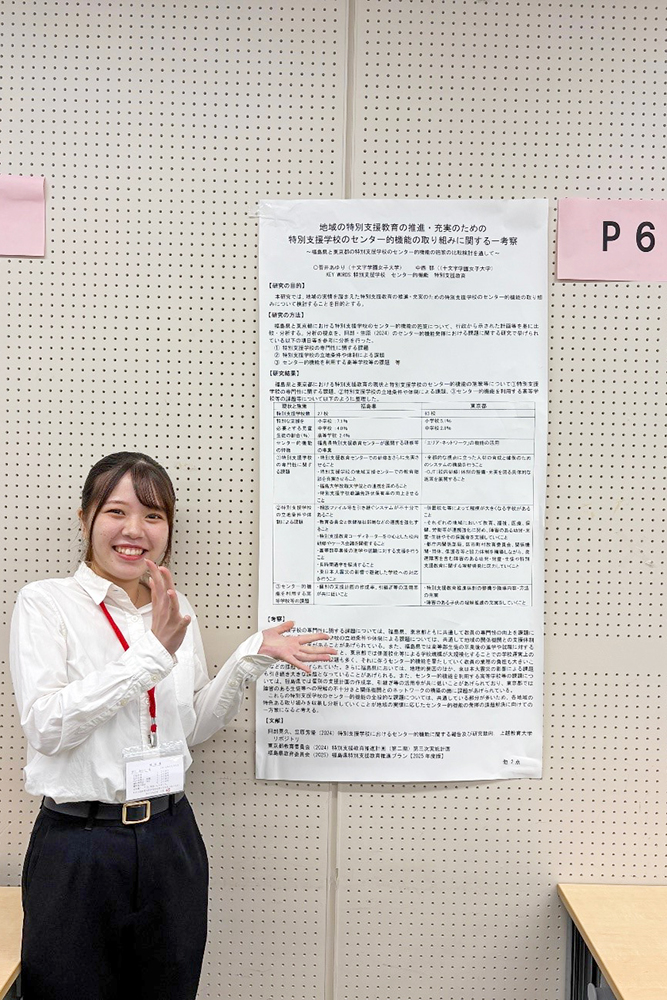
地域の実情を踏まえた特別支援教育の推進・充実のための特別支援学校のセンター的機能の取り組みについて検討いたしました。検討方法として福島県と東京都における特別支援学校のセンター的機能の施策について、行政から示された計画等を基に比較・分析しました。分析の視点として、阿部・笠原(2024)のセンター的機能発揮における課題に関する研究で挙げられている3つの項目(①特別支援学校の専門性に関する課題、②特別支援学校の立地条件や体制による課題、③センター的機能を利用する高等学校等の課題)等を参考に分析をしました。
ポスター発表では、福島県にある大学の先生や学生の参加者もあり、福島県のセンター的機能の取り組みについて多くの質問がありました。また、センター的機能の充実について多くのご意見をいただき、今後の研究に活かしていきたいと思っています。
ポスター発表では、福島県にある大学の先生や学生の参加者もあり、福島県のセンター的機能の取り組みについて多くの質問がありました。また、センター的機能の充実について多くのご意見をいただき、今後の研究に活かしていきたいと思っています。
知的障害の児童等における自立活動の指導に関する一考察
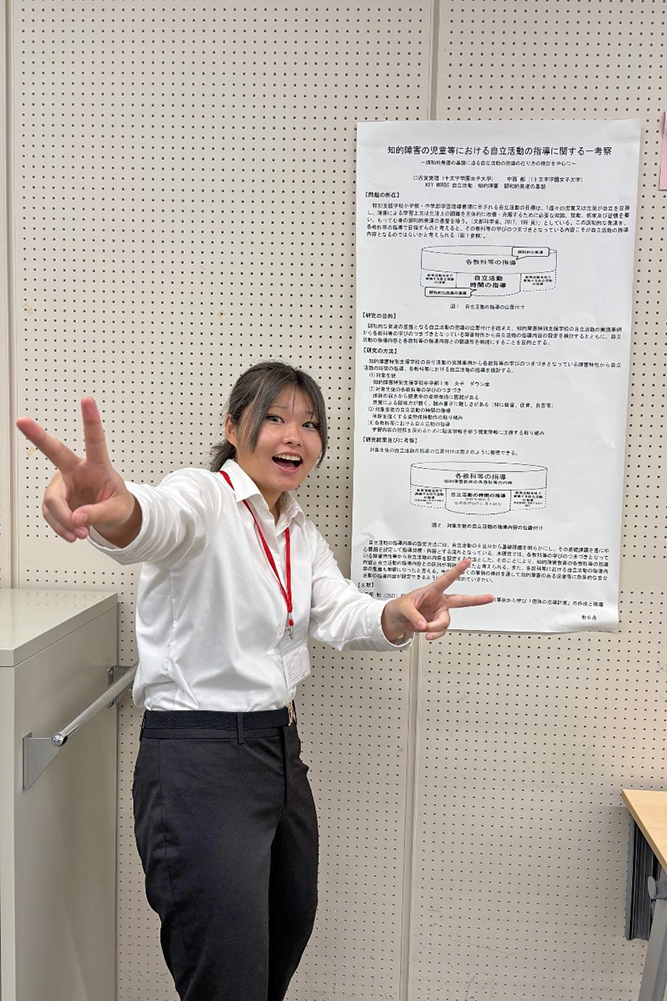
全国特別支援学校知的障害教育校長会報告(2024)では、自立活動の授業時間を特設し、週時程に位置付けている学校は小学部で522校(82.6%)、中学部で506校(80.7%)と、約2割の学校で自立活動を特設した授業に位置付けた指導が実施されていない状況にあります。この現状を踏まえ、知的障害特別支援学校の各教科等の学びのつまづきとなっている障害特性のうち各教科等の調和的な発達の基盤となる内容を自立活動の指導として設定していくことを検討しました。そのうえで、自立活動の指導内容と各教科等の指導内容との関連性を明確にした指導事例を紹介しました。
ポスター発表では、知的障害特別支援学校で特設の自立活動の時間の指導が進まないことへの研究は多く取り組まれているので、先行研究を丁寧に読み解いていくことが深まりのある研究となるとアドバイスをいただきました。
ポスター発表では、知的障害特別支援学校で特設の自立活動の時間の指導が進まないことへの研究は多く取り組まれているので、先行研究を丁寧に読み解いていくことが深まりのある研究となるとアドバイスをいただきました。
障害のある児童等の思考力・判断力・表現力等を育む授業づくりに関する一考察
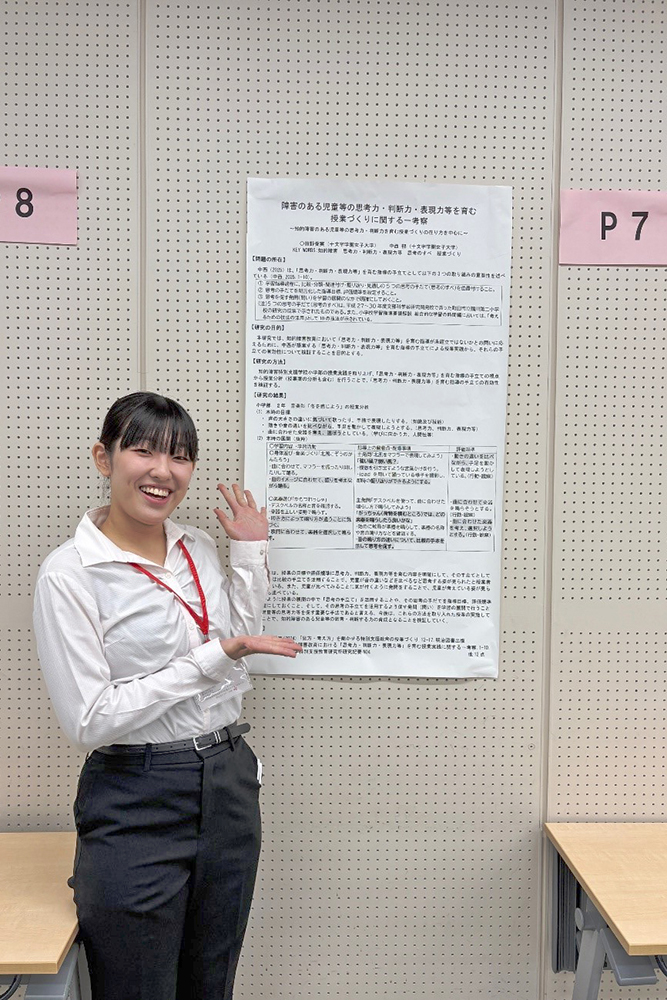
知的障害教育において「思考力・判断力・表現力等」を育む指導が未確立ではないかとの問いに応えるために、中西(2025)が提案する「思考力・判断力・表現力等」を育む指導の手立て(学習指導過程に、「比較・分類・関連付け・振り返り・見通す」の5つの思考の手だて(思考のすべ)を位置付けること。② 思考の手だてを明言化した指導目標、評価規準を設定すること。③ 思考を促す発問(問い)を学習の展開のなかで明確にしておくこと。)による授業実践から、それらの手立ての有効性について検証しました。
ポスター発表では、知的障害の児童等が授業で思考している姿をどのように捉え評価していくのかをさらに研究していくようアドバイスをいただきました。
ポスター発表では、知的障害の児童等が授業で思考している姿をどのように捉え評価していくのかをさらに研究していくようアドバイスをいただきました。

ポスター発表でのご指導を今後の研究に活かして、特別支援学校、小学校の教師になって、研究を子ども達の指導に活用していけるようにしていきます。