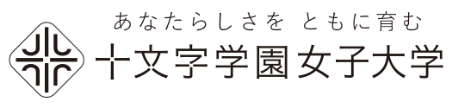公開講座実施報告(2024)
11月16日(土)に、土井善晴副学長による公開講座、おいしいものセミナー lesson5「心に残す食事 ~私たちと自然の間にあるもの~ 」を開催しました
土井家のお節料理の写真も公開
11月16日(土)、土井善晴先生(料理研究家・本学副学長)の公開講座「土井善晴のおいしいものセミナー lesson5 『心に残す食事 ~私たちと自然の間にあるもの~』」を開催いたしました。当日は、新潟県や三重県など遠方からの参加者もあり、200人を超える方々にご来場いただきました。
講演では、土井先生が撮影された四季折々の食材の写真がスクリーンに映し出され、素材本来のおいしさを引き出す料理の方法や、日々の食事に対する考え方など、たくさんの話題が次々と展開されました。
参加者からの質問コーナーでは、「土井先生の最後の晩餐は?」というお声が挙がり、「炊きたてのご飯、味噌汁、漬け物!」と土井先生らしいお答えに、会場の皆さまは納得の表情を浮かべていました。
ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。
11月16日(土)、土井善晴先生(料理研究家・本学副学長)の公開講座「土井善晴のおいしいものセミナー lesson5 『心に残す食事 ~私たちと自然の間にあるもの~』」を開催いたしました。当日は、新潟県や三重県など遠方からの参加者もあり、200人を超える方々にご来場いただきました。
講演では、土井先生が撮影された四季折々の食材の写真がスクリーンに映し出され、素材本来のおいしさを引き出す料理の方法や、日々の食事に対する考え方など、たくさんの話題が次々と展開されました。
参加者からの質問コーナーでは、「土井先生の最後の晩餐は?」というお声が挙がり、「炊きたてのご飯、味噌汁、漬け物!」と土井先生らしいお答えに、会場の皆さまは納得の表情を浮かべていました。
ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。


11月30日(土)に、公開講座「どうなる!?子どもの心とからだ ―最新の全国調査結果をふまえて―」を開催しました
11月30日(土)、十文字学園女子大学で公開講座「どうなる!?子どもの心とからだ ―最新の全国調査結果をふまえて―」を開催しました。
幼児教育学科が共催である本講座は、母子健康手帳掲載の「発育グラフ」の作成などに携わり、子どもの健康や育ちに係る研究に従事してきた加藤先生が、今年10月公表予定であった「令和5年乳幼児身体発育調査」の結果を含めた内容をお話しする予定でしたが、公表が延期となったため、「令和3年幼児健康度調査」の結果を交えた講演となりました。
幼児教育学科が共催である本講座は、母子健康手帳掲載の「発育グラフ」の作成などに携わり、子どもの健康や育ちに係る研究に従事してきた加藤先生が、今年10月公表予定であった「令和5年乳幼児身体発育調査」の結果を含めた内容をお話しする予定でしたが、公表が延期となったため、「令和3年幼児健康度調査」の結果を交えた講演となりました。

加藤 則子 特任教授

前半は、『最近の子どもの発育、発達の特徴』として、「外遊びができなくなると運動不足となる。災害や社会環境(コロナ禍)の変化に子どもの発達や発育は影響を受けること」や、『最近の子どもの生活と健康の特徴』として、「屋内遊びが増え、スマホやパソコンに費やすスクリーンタイムの影響が注目されていること」について話されました。福島県では東日本大震災(2011年)の影響により、翌年以降6歳児の肥満が増加したことや、沿岸周辺の浜通り・中通りでは肥満割合増加が著しく、内陸の会津ではそれほどの増加が見られなかったことから、地域によって放射線への忌避が影響している可能性も指摘されました。
後半は、『最近の出生体重の減少と若い女性のやせ』について、「日本では30年にわたり出生体重が減少しており、低出生体重に影響を及ぼす要因や栄養・健康づくりの考え方が変化してきている」という結果に、参加した学生たちも真剣に聞き入っていました。
最後には、『母子健康の変遷』について、保健指導用イメージと母子健康手帳に掲載してあるグラフを提示しながら、「子どもにとってストレスのある環境や状態、時代背景は、発育に影響を及ぼすので、調査での数字に現れない課題にも注視が必要である」とまとめられ、受講者に深い印象を与えました。
講演後は受講者からの質問を、コーディネーターである幼児教育学科の向井美穂教授が加藤特任教授に投げかけ、「スクリーンタイムの影響」や「成長曲線から外れた子どもの対応、医療機関へのつなぎ方」などについて応答が行われた後、受講者からの感想を全体で共有し講座を締めくくりました。
当日は短大卒業後、久しぶりに来校した卒業生の姿も見られました。キャンパスの充実ぶりに驚きながら、学内の写真を撮っていました。そのような卒業生と学生スタッフとして関わった在校生、幼児教育学科の教員が連携し、そのつながりが会場の和やかな雰囲気を醸し出していました。
最後には、『母子健康の変遷』について、保健指導用イメージと母子健康手帳に掲載してあるグラフを提示しながら、「子どもにとってストレスのある環境や状態、時代背景は、発育に影響を及ぼすので、調査での数字に現れない課題にも注視が必要である」とまとめられ、受講者に深い印象を与えました。
講演後は受講者からの質問を、コーディネーターである幼児教育学科の向井美穂教授が加藤特任教授に投げかけ、「スクリーンタイムの影響」や「成長曲線から外れた子どもの対応、医療機関へのつなぎ方」などについて応答が行われた後、受講者からの感想を全体で共有し講座を締めくくりました。
当日は短大卒業後、久しぶりに来校した卒業生の姿も見られました。キャンパスの充実ぶりに驚きながら、学内の写真を撮っていました。そのような卒業生と学生スタッフとして関わった在校生、幼児教育学科の教員が連携し、そのつながりが会場の和やかな雰囲気を醸し出していました。

参加者は真剣に耳を傾けていました

趣味であるフラメンコのポーズを披露し会場を和ませる場面も
幼児教育学科教員と加藤先生の集合写真
受講者の感想(一部)
- 子どもの発育や生活・健康は社会情勢が反映されていることを数値で知ることができました。講演を聞き、健やかな発達を考える機会になりました。
- 「私の研究はコツコツとしたものである」と先生はお話しされていましたが、このような調査研究が育児を支える大切なものだと感じました。
- SNSでもダイエットに関する情報が多く、私や友だちもダイエットを気にしている子が多いですが、痩せすぎてしまうと母体や胎児に影響があることが分かりました。将来出産するうえで、今、健康に生活することが大切であることを学びました。
9月14日(土)に、公開講座 「平安朝の恋文-書道と文学のコラボレーション-」を開催しました

赤間恵都子名誉教授(左)と鷹野理芳氏(右)
9月14日(土)に、書道家で本学の非常勤講師である鷹野理芳氏と本学の赤間恵都子名誉教授を講師に、公開講座「平安朝の恋文-書道と文学のコラボレーション-」を開催しました。
今回の講座は、『源氏物語』をテーマとして物語に登場する姫君の筆跡の再現を続けてこられた鷹野先生と、平安女流文学を専門にする赤間先生のお2人の熱い思いにより実現したコラボレーション企画となりました。
本講座では、「恋文」をテーマに、それぞれのアプローチから「平安朝の恋文」を読み解きました。
今回の講座は、『源氏物語』をテーマとして物語に登場する姫君の筆跡の再現を続けてこられた鷹野先生と、平安女流文学を専門にする赤間先生のお2人の熱い思いにより実現したコラボレーション企画となりました。
本講座では、「恋文」をテーマに、それぞれのアプローチから「平安朝の恋文」を読み解きました。

当時の文の形式を紹介、文の折り方も様々でした

当時は野菊が主流でしたが、今回は大き目の菊を使い説明
講座の中で、鷹野先生が文(ふみ)をその場で再現する試みもありました。再現した文は、『枕草子』に書かれている「山吹の花の文」です。中宮定子から清少納言のもとに届きました。
届いた文は次のようなものでした。「紙にはものも書かせたまはず。山吹の花びらただ一重を包ませたまへり。それに、『言はで思ふぞ』と書かせたまへる」。現代語訳をしてみると「紙には何もお書きあそばされず、山吹の花びらただ一重をお包みあそばしていらっしゃる。それに『言はで思ふぞ』とお書きあそばされている」と解釈されます。「言はで思ふぞ」とは、「言葉に出さなくても、あなたのことを思っています」という意味です。
届いた文は次のようなものでした。「紙にはものも書かせたまはず。山吹の花びらただ一重を包ませたまへり。それに、『言はで思ふぞ』と書かせたまへる」。現代語訳をしてみると「紙には何もお書きあそばされず、山吹の花びらただ一重をお包みあそばしていらっしゃる。それに『言はで思ふぞ』とお書きあそばされている」と解釈されます。「言はで思ふぞ」とは、「言葉に出さなくても、あなたのことを思っています」という意味です。
今回は造花の山吹の花を用い、鷹野先生が「言はで思ふぞ」と実際に書くところを、書画カメラを通して参加者にも見ていただきました。「文中の『一重』という表現は、5弁ある花びら1つ1つに1文字ずつ記した可能性もあるが、1枚という意味でとらえ、小さな花びらの中に『言はで思ふぞ』と書いた可能性もある」という赤間先生の解説を聞きながら、鷹野先生がその実演を行う様子に、会場からは大きな拍手が起こりました。

5弁の花びらに1文字ずつ記した様子

写真右側は直径1cmの花びらに記した様子
さらに講座の最後には、講師それぞれが選んだ恋文をご紹介いただきました。鷹野先生は、『紫式部日記』から紫式部と藤原道長との恋文を、赤間先生は、『栄花物語』から皇后定子と一条天皇の恋文を選びました。鷹野先生は、「紫式部の直筆の書物は残っていないが、文や内容から、紫式部の仮名に対す考え方を学べる」と、書道家ならではの思いを語り、赤間先生は、「定子が最後に遺した文に対して、11年後に一条天皇が答えた文は時空を超えた究極の恋文だと感じる」と、文学的な観点からお話をされました。
また、今回初めての試みとして、学内に鷹野先生の「書」を展示した特設ギャラリーを設置しました。参加者の皆様には、先生方の解説に加えて、間近で「書」に触れていただく機会となりました。古典を手本に書くことを「臨書」と言いますが、穂苅先生は「臨書」について、「当時の美意識に触れ、昔の人々とコミュニケーションが取れるように感じる」と述べられました。

特設ギャラリーの様子

公開講座会場前にも多数の作品を展示
今回は、現在放映中の大河ドラマ『光る君へ』(NHK)にもフォーカスし、登場する人物が残した書、あるいはその人物が著したと伝わる書についても触れていただきました。現在のように、メールやスマートフォンがない時代、「文」は必要不可欠なものでした。その文1つ1つにも形式があり、紙や色を変えたり花を添えたりと、送る相手のことを考えたやりとりがなされたものです。
講師の先生のお話から、その情景が目に浮かび、時を越えて平安時代の「華やかさ」、「雅さ」に触れた講座となりました。
講師の先生のお話から、その情景が目に浮かび、時を越えて平安時代の「華やかさ」、「雅さ」に触れた講座となりました。

鷹野先生の作品の前で、講師の先生方と文芸文化学科の学生スタッフたち
当日の様子