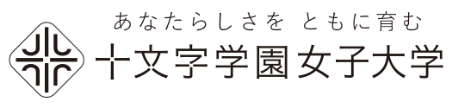十文字学園女子大学における生成AI利用ガイドライン
1. 本学の考え方
生成AIについては、大変便利であるため多くの人が活用し、また様々な企業により開発が行われている状況にあります。生成AIは「人間の知性や生産性の拡張」をもたらす可能性がある一方で、生成AIはまだまだ開発途上の技術であり、個人情報、組織の要機密情報、他者の著 作物等を入力してよいかといった「入力データと法令との関係」や、「生じるリスク」、「出力されたものと入力したものとの権利の関係性」等を理解した上で活用する必要があります。 本学においても学生教育や研究の分野における生成AIの活用にあたっては、学生の皆さんの修学に悪影響を及ぼす可能性、研究における剽窃、業務における機密情報の漏洩等様々なことに留意する必要があります。そして、これらの理解は、生成AI の原理への理解、生成 AI へのプロンプト(質問・作業指示)に関する工夫やそれによる出力の検証等、生成AIを使いこなすことやそれ自体の研究を行う上でも欠かせません。
そのため、今回、本学の学生・教職員に向け本学における生成AI利用のためのガイドラインを作成いたしました。本ガイドラインの構成は、本学の業務で生成AIを利活用する際に注意すべき事項を示した全体の方針、留意点を軸に、教育、研究、業務の観点においてそれぞれ考慮、留意すべき事項をまとめています。生成AIを業務に利活用する前に自身に関連する内容を必ず確認ください。
そのため、今回、本学の学生・教職員に向け本学における生成AI利用のためのガイドラインを作成いたしました。本ガイドラインの構成は、本学の業務で生成AIを利活用する際に注意すべき事項を示した全体の方針、留意点を軸に、教育、研究、業務の観点においてそれぞれ考慮、留意すべき事項をまとめています。生成AIを業務に利活用する前に自身に関連する内容を必ず確認ください。
2. 方針・留意点等 (全体の方針)
基本的に、本学においては、生成AIの活用を推進すべきと考えます。しかしながら、学生の修学の妨げや、研究者の研究不正、業務に係る秘密保持等の観点から、その活用には一定の制限を設けることとします。
(留意点)
【データ入力に際して注意すべき事項】
生成 AI を利用しデータを入力する際に注意すべき事項は、以下のとおりです。
「入力を禁止するもの」と「注意を要するもの」に分けて記載します。
・入力を禁止するもの
(1)個人情報
理由:個人情報保護法に違反する可能性があるため
(2)他社から秘密保持義務を課されて開示された秘密情報
理由:秘密保持契約に違反する可能性があるため
(3)その他の本学の要機密情報
理由:法令上保護される権利を失う可能性があるため
・注意を要するもの
(1)第三者が著作権を有しているデータ(他人が作成した文章等)
理由:使用方法によっては、著作権侵害となる可能性があり得るため
(2)登録商標・意匠(ロゴやデザイン)
理由:生成物を使用した場合、登録商標、意匠の調査を要するため
(3)著名人の顔写真や氏名
理由:生成物を使用した場合、パブリシティ権侵害に該当するため
【生成物を利用する際に注意すべき事項】
生成 AI が生成した生成物を利用する際は、以下の注意事項を十分確認の上使用ください。
(1) 生成物の内容に虚偽や誤りが含まれている可能性がある
(2) 生成物を利用する行為が誰かの既存の権利を侵害する可能性がある
① 著作権侵害
② 商標権・意匠権侵害
③ 虚偽の個人情報・名誉毀損等
(3)生成物について著作権が発生しない可能性がある
(4)生成物を商用利用できない可能性がある
(5)生成 AI のポリシー上の制限に注意する
※上記の事項は主にChatGPTを想定し記載しておりますが、生成AIはChatGPTだけではありません。例えば、ChatGPTにおいては、現時点で商用利用に制限はありませんが将来的にポリシーが変わる可能性は十分にあり得ます。また、法改正に伴う変更なども今後行われる可能性があります。 そのため、どのような生成AIを用いる場合であっても、関連する法律や使用する生成AIのポリシーを 理解した上で利用ください。
なお、上記は、一般社団法人 日本ディープラーニング協会が公表している「生成 AI の利用ガイドライン」を参考に作成しています。同ガイドラインにおいて、各項目の解説がありますので、参照ください。
※現在のChatGPT のような約款型クラウドサービス(不特定多数の利用者に対して提供する、定型約款や規約等への同意のみで利用可能となるクラウドサービス)では、セキュリティ対策やデータの取扱いなどについて本学への特別な扱いを求めることができない場合が多く、必要十分なセキュリティ要件を満たすことが一般的に困難であることから、要機密情報を取り扱うことはできません(ただし、大学として契約しているクラウドサービスは除きます)。
(留意点)
【データ入力に際して注意すべき事項】
生成 AI を利用しデータを入力する際に注意すべき事項は、以下のとおりです。
「入力を禁止するもの」と「注意を要するもの」に分けて記載します。
・入力を禁止するもの
(1)個人情報
理由:個人情報保護法に違反する可能性があるため
(2)他社から秘密保持義務を課されて開示された秘密情報
理由:秘密保持契約に違反する可能性があるため
(3)その他の本学の要機密情報
理由:法令上保護される権利を失う可能性があるため
・注意を要するもの
(1)第三者が著作権を有しているデータ(他人が作成した文章等)
理由:使用方法によっては、著作権侵害となる可能性があり得るため
(2)登録商標・意匠(ロゴやデザイン)
理由:生成物を使用した場合、登録商標、意匠の調査を要するため
(3)著名人の顔写真や氏名
理由:生成物を使用した場合、パブリシティ権侵害に該当するため
【生成物を利用する際に注意すべき事項】
生成 AI が生成した生成物を利用する際は、以下の注意事項を十分確認の上使用ください。
(1) 生成物の内容に虚偽や誤りが含まれている可能性がある
(2) 生成物を利用する行為が誰かの既存の権利を侵害する可能性がある
① 著作権侵害
② 商標権・意匠権侵害
③ 虚偽の個人情報・名誉毀損等
(3)生成物について著作権が発生しない可能性がある
(4)生成物を商用利用できない可能性がある
(5)生成 AI のポリシー上の制限に注意する
※上記の事項は主にChatGPTを想定し記載しておりますが、生成AIはChatGPTだけではありません。例えば、ChatGPTにおいては、現時点で商用利用に制限はありませんが将来的にポリシーが変わる可能性は十分にあり得ます。また、法改正に伴う変更なども今後行われる可能性があります。 そのため、どのような生成AIを用いる場合であっても、関連する法律や使用する生成AIのポリシーを 理解した上で利用ください。
なお、上記は、一般社団法人 日本ディープラーニング協会が公表している「生成 AI の利用ガイドライン」を参考に作成しています。同ガイドラインにおいて、各項目の解説がありますので、参照ください。
※現在のChatGPT のような約款型クラウドサービス(不特定多数の利用者に対して提供する、定型約款や規約等への同意のみで利用可能となるクラウドサービス)では、セキュリティ対策やデータの取扱いなどについて本学への特別な扱いを求めることができない場合が多く、必要十分なセキュリティ要件を満たすことが一般的に困難であることから、要機密情報を取り扱うことはできません(ただし、大学として契約しているクラウドサービスは除きます)。
3.業務等における個別の観点
〇教育の観点
【学修における留意事項(学生向け)】
生成AIの利用については、様々な立場がありますが、重要なのは、自身が主体的に学び、その学びを深めていくことです。これまでも、これからも新しい技術やツールを利用・活用していくことは不 可避であると思われますが、生成AIの利用・活用に際しては、特に以下の事項に注意してください。
(1)生成AIに依存しすぎると自身の学びに繋がらない。
(2)生成AIの活用方法として、例えば、自身のアイディアを拡げる・深めるための仮想の相手 にするといったような、「自ら主体的に学ぶ」ことを補助するツールとして利用することが考 えられる。
(3)意図せず剽窃等の研究不正に当たる場合があるため、また、自身の学びに繋がらないため、生成AIの出力結果をそのままレジュメ、発表資料、レポート卒業論文等に用いてはならない。
(4)生成AIを利用した際は、利用した事実や生成AIを利用した該当箇所等を明記しなければならない場合がある。
(5)生成AIの出力結果を鵜呑みにせず、妥当性や信頼性を確認し、責任を持って利用する。
(6)生成AIへの情報入力を介して、意図しない情報流出・漏洩が生じるおそれがあることを理解した上で利用する。
(7)授業等における生成AI利用の可否は、それぞれの授業科目によって異なることがあるため、生成AIを利用する際は、事前に担当教員や指導教員に確認する。
【教育における留意事項(教員向け)】
学生の生成AIの利用をコントロールすることは困難であり、その利用を完全に排除することは現実的ではないと思われます。まず、教員自身が、生成AIに何ができて何ができないのかについて理解を深めた上で、生成AIの利用について向き合うことが必要であると思われます。 生成AIは、利用の仕方によっては、作業効率や教育効果の向上が期待できる一方、学生自 身の学びの促進や厳格な成績評価に係わって大きな問題が生じることも懸念されます。 教育目標を達成し、学生が学位授与方針に掲げられた諸能力を獲得できるよう、以下の事項 を念頭に置きながら教育を実施する必要があると考えられます。
(1)教員自らが生成AIの出力結果に対する理解を深める。例えば、レポート課題をプロンプトとして入力し、出力を評価してみる。こうしたプロセスを学生と共有する、さらには学生に 改善させることで、生成AIの利点と限界を学生自身に考えさせる良い機会となるかもしれません。
(2)課題の出題方法を工夫する。例えば、単に事実を記述させるようなレポートは避け、最終成果のみを提出させるのではなく、課題を分割する、学生同士または教員からのフィー ドバックを取り込むなど、レポート作成の過程を評価する等の工夫が考えられる。
(3)課題を授業時間外とせずに、授業時間内に記述させる形式にする、少人数の授業であれば、口頭での説明を求めることも可能である。
(4)レポートのみでの評価は避けて、可能な範囲でテストや口述試験を組み合わせ、多様な観点から評価を行う。
(5)レポート等、課題の提出を求める際は、生成AIの利用の可否、あるいは条件等について明確な指示を与える。
(6)ルールを守らなかった場合の対応について明確にした上で、適切に利用するよう注意喚起する。
(7)生成AIのリスクについて注意喚起する。
〇研究の観点
研究活動においても、生成AIのような新しい技術やツールの研究活動における有効利用を図りつつも、その利用にあたっては関連する法律や研究倫理に反しない範囲内で責任を持って利用する必要があります。そこで、本学の研究活動における生成AIの利用においては、原則的に以下の点に沿って利用することとします。
【論文等の記述内容】
論文等の記述内容については、生成AIの使用有無に関わらず、研究者の責任であることを認識し、研究不正や権利侵害(著作権、肖像権、商標権、意匠権など)が生ずる恐れがある場合には使用しない。
★特に注意を要する点
【個人情報、機密情報等への対応】
生成AI への入力を通じて個人情報や要機密情報等が流出・漏洩する恐れがある場合には使用しない。
★特に注意を要する点
〇業務の観点
業務において生成AIを利活用することは教職員の業務効率化につながる可能性があるため、今後、様々な場面において利活用することが想定されますが、「留意点(1~2頁)」に記載された問題を引き起こす可能性があることを理解した上で、以下の事項をよくご確認いただき、学内規則に 則った利活用を検討ください。
(1)個人情報や要機密情報の流出には十分留意し、安易な利活用はしないように心がけてく ださい。
(2)生成AIによって作成された文章には、虚偽や矛盾、不適切な表現、他者が著作権を有す
るもの等が含まれている可能性があります。作成された文章を業務上利活用する前には、 作成者自身がよく確認した上で、その内容を理解・評価し、修正や加筆を行うよう注意し てください。
(3)教職員が日々、生成AIをめぐる議論や使用時の注意に関する最新の動向を把握しなが ら、データリテラシーを持って行動することを求めます。
【学修における留意事項(学生向け)】
生成AIの利用については、様々な立場がありますが、重要なのは、自身が主体的に学び、その学びを深めていくことです。これまでも、これからも新しい技術やツールを利用・活用していくことは不 可避であると思われますが、生成AIの利用・活用に際しては、特に以下の事項に注意してください。
(1)生成AIに依存しすぎると自身の学びに繋がらない。
(2)生成AIの活用方法として、例えば、自身のアイディアを拡げる・深めるための仮想の相手 にするといったような、「自ら主体的に学ぶ」ことを補助するツールとして利用することが考 えられる。
(3)意図せず剽窃等の研究不正に当たる場合があるため、また、自身の学びに繋がらないため、生成AIの出力結果をそのままレジュメ、発表資料、レポート卒業論文等に用いてはならない。
(4)生成AIを利用した際は、利用した事実や生成AIを利用した該当箇所等を明記しなければならない場合がある。
(5)生成AIの出力結果を鵜呑みにせず、妥当性や信頼性を確認し、責任を持って利用する。
(6)生成AIへの情報入力を介して、意図しない情報流出・漏洩が生じるおそれがあることを理解した上で利用する。
(7)授業等における生成AI利用の可否は、それぞれの授業科目によって異なることがあるため、生成AIを利用する際は、事前に担当教員や指導教員に確認する。
【教育における留意事項(教員向け)】
学生の生成AIの利用をコントロールすることは困難であり、その利用を完全に排除することは現実的ではないと思われます。まず、教員自身が、生成AIに何ができて何ができないのかについて理解を深めた上で、生成AIの利用について向き合うことが必要であると思われます。 生成AIは、利用の仕方によっては、作業効率や教育効果の向上が期待できる一方、学生自 身の学びの促進や厳格な成績評価に係わって大きな問題が生じることも懸念されます。 教育目標を達成し、学生が学位授与方針に掲げられた諸能力を獲得できるよう、以下の事項 を念頭に置きながら教育を実施する必要があると考えられます。
(1)教員自らが生成AIの出力結果に対する理解を深める。例えば、レポート課題をプロンプトとして入力し、出力を評価してみる。こうしたプロセスを学生と共有する、さらには学生に 改善させることで、生成AIの利点と限界を学生自身に考えさせる良い機会となるかもしれません。
(2)課題の出題方法を工夫する。例えば、単に事実を記述させるようなレポートは避け、最終成果のみを提出させるのではなく、課題を分割する、学生同士または教員からのフィー ドバックを取り込むなど、レポート作成の過程を評価する等の工夫が考えられる。
(3)課題を授業時間外とせずに、授業時間内に記述させる形式にする、少人数の授業であれば、口頭での説明を求めることも可能である。
(4)レポートのみでの評価は避けて、可能な範囲でテストや口述試験を組み合わせ、多様な観点から評価を行う。
(5)レポート等、課題の提出を求める際は、生成AIの利用の可否、あるいは条件等について明確な指示を与える。
(6)ルールを守らなかった場合の対応について明確にした上で、適切に利用するよう注意喚起する。
(7)生成AIのリスクについて注意喚起する。
〇研究の観点
研究活動においても、生成AIのような新しい技術やツールの研究活動における有効利用を図りつつも、その利用にあたっては関連する法律や研究倫理に反しない範囲内で責任を持って利用する必要があります。そこで、本学の研究活動における生成AIの利用においては、原則的に以下の点に沿って利用することとします。
【論文等の記述内容】
論文等の記述内容については、生成AIの使用有無に関わらず、研究者の責任であることを認識し、研究不正や権利侵害(著作権、肖像権、商標権、意匠権など)が生ずる恐れがある場合には使用しない。
★特に注意を要する点
- 情報の真偽確認:生成AIの出力には、事実ではない内容が含まれている場合があることに留意し、真偽の確認を徹底する
- 情報の出典確認:生成AIの出力には、出典が不明な内容や他者の著作物の一部が含まれている場合があることに留意し、出典等の確認を徹底する
- 情報の客観性確認:生成AIの出力は、世論やトレンド等を正確に反映していない場合があ ることに留意し、情報の客観性の確認を徹底する(人種、民族、性別、政治的立場等につい て、差別や偏った意見等を一般的世論と過信することがないように留意する)
【個人情報、機密情報等への対応】
生成AI への入力を通じて個人情報や要機密情報等が流出・漏洩する恐れがある場合には使用しない。
★特に注意を要する点
- 個人情報は入力しない
- 要機密情報(未公開の論文、特許出願に関する情報等を含む)は入力しない。
〇業務の観点
業務において生成AIを利活用することは教職員の業務効率化につながる可能性があるため、今後、様々な場面において利活用することが想定されますが、「留意点(1~2頁)」に記載された問題を引き起こす可能性があることを理解した上で、以下の事項をよくご確認いただき、学内規則に 則った利活用を検討ください。
(1)個人情報や要機密情報の流出には十分留意し、安易な利活用はしないように心がけてく ださい。
(2)生成AIによって作成された文章には、虚偽や矛盾、不適切な表現、他者が著作権を有す
るもの等が含まれている可能性があります。作成された文章を業務上利活用する前には、 作成者自身がよく確認した上で、その内容を理解・評価し、修正や加筆を行うよう注意し てください。
(3)教職員が日々、生成AIをめぐる議論や使用時の注意に関する最新の動向を把握しなが ら、データリテラシーを持って行動することを求めます。
4. その他・今後の進め方等
本ガイドラインが対象とする生成AIは、ChatGPTに限らずすべての生成AIを対象とします。また、本ガイドラインは、技術の進展や関係省庁の示す指針等の運用状況などに応じて、適宜見直しを行います。
十文字学園女子大学長 安達一寿