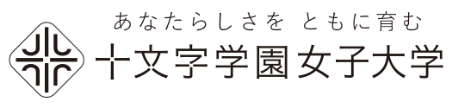卒業研究題目
文芸文化学科では,4年次に卒業研究を提出します。4年間の学びの集大成となります。これまでの卒業研究題目(一部)をご紹介します。
日本文学・英米文学・民俗学
| 『源氏物語』のにおい ―薫の香りの物語内での役割とは― |
| 紀貫之の和歌の特性の分析 |
| 境界としての橋 ―橋姫と人柱― |
| 文学史・装幀からみる『月に吠える』 |
| 夢野久作「地獄」論 |
| 人称代名詞からみる村上春樹初期作品は逃避なのか |
| わらべうたとイギリス童謡の比較研究 |
| アンデルセン挿話における少女像とは -『雪の女王』を中心に- |
| ピーター・パンの妖精 ―ティンカー・ベルのモデル像― |
| 『不思議の国のアリス』から読み解く作者の意図について ―ヴィクトリア朝の児童観と教育から考察する― |
| 高畠華宵と少年少女たち ―児童雑誌から見る華宵作品― |
| ケストナー「飛ぶ教室」の日本語訳比較からみる児童小説 |
| アイヌ民族の動物観 ―口承文芸を中心に― |
| 怪異のエンターテイメント化 ―妖怪文化の変容― |
| 伝統行事・流鏑馬の研究 |
| 地域伝承の研究 ―温羅と吉備津彦をめぐって― |
言語・日本語・ことば
| 漫画『ドラえもん』のひみつ道具のネーミング研究 ―語彙・表記の研究を中心に― |
| 一文の中に込められた編集者たちの想い ―アニメ雑誌のキャッチコピーから分析する― |
| アイスクリームのパッケージ分析 ―言語の面に着目して― |
| 坂道グループにおけるコンセプトと歌詞の共通点について |
| 広告媒体による映画のキャッチコピー比較 ―キャッチコピーを複数持つ映画を例に― |
| 漫画内における役割語とオノマトペが与える影響について ―『動物のお医者さん』を資料にして― |
| 異なるコミュニケーション場面での言葉遣いの比較 ―話し手がどのような配慮を行っているのか、聞き手はどのような印象を持つのか― |
| 日本語における男性語と女性語について |
美術・芸術・舞台
| カラヴァッジョの作品における天使とキューピッドの羽の構造について |
| ルネ・マグリットの初期コラージュ的技法とモチーフについて |
| クロード・モネの「眼」と白内障罹患後のモネの見た自然 |
| ミュージカル『刀剣乱舞』における歴史の守り方についての考察 |
| ミュージカル『オペラ座の怪人』における”怪人”の捉え方と日英比較 ―台詞・歌詞から考える言葉の意味― |
| バンクシーを軸に考える現代アートの価値について ―美的価値と経済的価値2つの側面― |
| 舞台『Sleep No More』から見たコンテンポラリーダンス |
| ミュージカル『エリザベート』人物像の比較 |
| 舞台比較 2.5次元舞台とストレートプレイの比較 |
社会・文化・多文化
| 文化を未来へつなぐボーカロイド ―ボーカロイドは「続くコンテンツ」か― |
| 「推しカラー」がもたらす心理的変化について |
| ヤングケアラーの実態と私たちの思い違い |
| 「キャラクター」と「ロゴ」の役割と活用 ―埼玉県の基礎自治体に焦点を当てて― |
| ディズニー男性のキャラクターの表象研究 |
| 『ちゃお』連載作品から見る少女文化のひろがり |
| ディズニーアニメーションのジェンダ―表象の変容 ―ヒロインのルックス比較から― |
図書館・書店・出版
| 電子書籍の未来像を考える |
| 読者中心の図書館づくり ―多文化サービスの視点から― |
| 印刷技術と出版変革 ―江戸文化の「読む」を紐解く― |
| 学校図書館の可能性を拓く ―専門高校における「課題研究」を中心に― |
| 図書委員会の活動が生徒にもたらす影響 -埼玉県内における公立高等学校の場合- |
| セレクト型書店における本と人との関係性 -書店サービスがつくる「出会いの場」- |