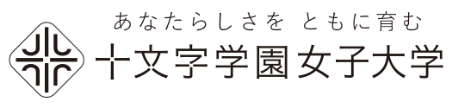ゆうこ先生の日本語学ひと口講座 ~歌詞とか菓子とか~

ふだん何気なく耳にしたり口ずさんだりしている歌詞を、ことばに注目して分析してみる日本語学のミニ講座。ついでに、大好きなお菓子のことも、ことばの観点から分析していきます。
たぶん、お菓子の話題が多めになる気がするような、しないような……。
講座内容は随時更新していきますので、時々のぞいてみてください。(担当:星野祐子)
たぶん、お菓子の話題が多めになる気がするような、しないような……。
講座内容は随時更新していきますので、時々のぞいてみてください。(担当:星野祐子)
2025年6月22日 更新
わたし( )気付いちゃいました―FRUITS ZIPPER『わたしの一番かわいいところ』
世界で最も包括的で権威ある英語辞典といえば、オックスフォード英語辞典(Oxford English Dictionary:OED)です。収録語数は約60万語を超え、日本語由来の語は、2024年4月時点で、575語登録されています。
今回注目する「かわいい」もその一つ(kawaiiは2010年の第3版から掲載)。「かわいい」は、キュートとは違う日本らしさを備えています。
さて、アイドル戦国時代と言われる昨今。
「かわいい」をコンセプトにしたアイドルが続々とデビューしています。
そんな「かわいい」を牽引しているアイドルプロジェクトが、「アソビシステム」による「KAWAII LAB.」。通称「カワラボ」です。
今回は「カワラボ」の第1弾アイドルの「FRUITS ZIPPER」から。
今回注目する「かわいい」もその一つ(kawaiiは2010年の第3版から掲載)。「かわいい」は、キュートとは違う日本らしさを備えています。
さて、アイドル戦国時代と言われる昨今。
「かわいい」をコンセプトにしたアイドルが続々とデビューしています。
そんな「かわいい」を牽引しているアイドルプロジェクトが、「アソビシステム」による「KAWAII LAB.」。通称「カワラボ」です。
今回は「カワラボ」の第1弾アイドルの「FRUITS ZIPPER」から。
FRUITS ZIPPER『わたしの一番かわいいところ』(2022)
「あれ気付いちゃいましたか?」で始まる『わたしの一番かわいいところ』は、これまで数々のアイドルやアーティストに楽曲を提供してきたヤマモトショウ氏によるもの。作詞・作曲・編曲ともにヤマモト氏が手がけています。それでは、サビの部分をみてみましょう。
【1番サビ】
わたしの一番、かわいいところに気付いてる
そんな君が一番すごいすごいよすごすぎる!
そして君が知ってるわたしが一番かわいいの、
わたしもそれに気付いた!
1番のサビでは、わたしの一番かわいいところを知っている君のすごさを、ストレートなことばで表しています。
推してくれる君がいるからこそ、アイドルとして輝ける。君のおかげで、アイドルとしてかわいい自分に気付くことができた、という流れでしょうか。
だから、最後のフレーズは「わたしもそれに気付いた!」です。
【2番サビ】
わたしの一番、かわいいところをよく見てる
そんな君がほんとに超ラッキーな人すぎる!
そして君が何年たってもそう思えるように
わたしはそれに気付いた
わたしを推している君は超ラッキーな人。そんなふうに無邪気に君を評します。
でも、わたしは気付きました。「何年たってもそう思えるように」今何をすべきか。
アイドル戦国時代だからこそ、永遠に推してもらうことは実は難しい。また、アイドルでいられる時間も永遠ではない。
君が何年たっても「わたしの一番、かわいいところ」をよく見ていて「超ラッキーな人」でいられるように、改めて、アイドルであるわたしは思索を深めます。
だからこそ、最後のフレーズは「わたしはそれに気付いた」なのでしょう。
1番サビと違って「!」がないところにも、「わたし」がアイドルとして理想の姿を維持していこう、と静かに決意している様子を想像することができます。
「も」と「は」の違いから、歌詞を読み解いてみました。
【1番サビ】
わたしの一番、かわいいところに気付いてる
そんな君が一番すごいすごいよすごすぎる!
そして君が知ってるわたしが一番かわいいの、
わたしもそれに気付いた!
1番のサビでは、わたしの一番かわいいところを知っている君のすごさを、ストレートなことばで表しています。
推してくれる君がいるからこそ、アイドルとして輝ける。君のおかげで、アイドルとしてかわいい自分に気付くことができた、という流れでしょうか。
だから、最後のフレーズは「わたしもそれに気付いた!」です。
【2番サビ】
わたしの一番、かわいいところをよく見てる
そんな君がほんとに超ラッキーな人すぎる!
そして君が何年たってもそう思えるように
わたしはそれに気付いた
わたしを推している君は超ラッキーな人。そんなふうに無邪気に君を評します。
でも、わたしは気付きました。「何年たってもそう思えるように」今何をすべきか。
アイドル戦国時代だからこそ、永遠に推してもらうことは実は難しい。また、アイドルでいられる時間も永遠ではない。
君が何年たっても「わたしの一番、かわいいところ」をよく見ていて「超ラッキーな人」でいられるように、改めて、アイドルであるわたしは思索を深めます。
だからこそ、最後のフレーズは「わたしはそれに気付いた」なのでしょう。
1番サビと違って「!」がないところにも、「わたし」がアイドルとして理想の姿を維持していこう、と静かに決意している様子を想像することができます。
「も」と「は」の違いから、歌詞を読み解いてみました。

チョコレートの歴史をたどってみると―チョコレートの表記
2月14日はバレンタインデーでした。
そういえば、このコラムのサブタイトルは「歌詞とか菓子とか」ですので、今回はチョコレートに注目してみます。
そういえば、このコラムのサブタイトルは「歌詞とか菓子とか」ですので、今回はチョコレートに注目してみます。
日本で最初にチョコレートを口にした人物は、17世紀末、伊達政宗の命によりヨーロッパに渡った支倉常長ではないかと言われています。ただし、当時のチョコレートは飲み物で、現在のような固形のチョコレートではありませんでした。その後、18世紀末には、長崎に伝わり、当時の資料に「しょくらあと」や「しょくらとを」との記載が確認されます。そして、明治6(1873)年、岩倉具視を中心とした「遣欧使節団」が、フランスのリヨンでチョコレート工場を見学。大久保利通や津田梅子もチョコレートを口にしました。
では、国内において、チョコレートの加工・販売はいつから始まったのでしょうか。東京日本橋區若松町 両國「米津風月堂」(現・東京風月堂)の米津松造氏によるものが最初だと言われています。明治11(1878)年12月の『かなよみ新聞』には、「貯古齢糖」として、「此は「カウヒー」の類にして頗る芳味ある滋養物の菓子なり 洋客は日々之を喫す」との説明書きが確認されます。
当時、「チョコレート」は、様々な漢字で表記されていました。「貯古齢糖」「猪口令糖」「知古辣他」「千代古齢糖」「血汚齢糖」などです。最後の当て字「血汚齢糖」は、「牛の乳を固めて作ったお菓子」が「牛の血」と誤解されたことに起因します。当て字は、漢字の本来の意味や読みを超えて使われるものですが、「血汚齢糖」は、音だけではなく、意味も伝えているようです。
そんな気の毒(?)なチョコレート。上記のような迷信に加え、日本での販売当初は、原料を輸入に頼っていたため、販売価格も高価で、一般大衆にはなかなか手の出ないものだったようです。
では、国内において、チョコレートの加工・販売はいつから始まったのでしょうか。東京日本橋區若松町 両國「米津風月堂」(現・東京風月堂)の米津松造氏によるものが最初だと言われています。明治11(1878)年12月の『かなよみ新聞』には、「貯古齢糖」として、「此は「カウヒー」の類にして頗る芳味ある滋養物の菓子なり 洋客は日々之を喫す」との説明書きが確認されます。
当時、「チョコレート」は、様々な漢字で表記されていました。「貯古齢糖」「猪口令糖」「知古辣他」「千代古齢糖」「血汚齢糖」などです。最後の当て字「血汚齢糖」は、「牛の乳を固めて作ったお菓子」が「牛の血」と誤解されたことに起因します。当て字は、漢字の本来の意味や読みを超えて使われるものですが、「血汚齢糖」は、音だけではなく、意味も伝えているようです。
そんな気の毒(?)なチョコレート。上記のような迷信に加え、日本での販売当初は、原料を輸入に頼っていたため、販売価格も高価で、一般大衆にはなかなか手の出ないものだったようです。

怪獣の願い―合唱曲『怪獣のバラード』
私は、学科のなかで教職課程を担当しています。そのため、教育実習訪問で中学校を訪れることが結構あります。活気のある校舎に足を踏み入れると、中学校の教員を目指していた大学生の自分を思い出します。
この秋に訪れた中学校では、ちょうど合唱の練習をしていました。ということで、今日は合唱の曲から。
この秋に訪れた中学校では、ちょうど合唱の練習をしていました。ということで、今日は合唱の曲から。
岡田冨美子(作詞)『怪獣のバラード』(1972)
合唱コンクールの定番の曲です。サビ前のフレーズに注目してみます。
「海がみたい 人を愛したい 怪獣にも 心があるのさ」
このフレーズでは、怪獣がしたいことが2つ挙げられています。砂漠に住む怪獣の願いは、海を見ることと、人を愛すこと。そう、海を見ること……。実は、「海がみたい」は、「海をみたい」と言い換えることができます。
砂漠にいる怪獣だからこそ「見たいもの」と言えば「海」なのでしょう。ここでの「が」には、「他のものではなく、海こそが見たいものなんだ」という意味、つまり、排他の意味を感じとることができます。
「~が(し)たい」と「~を(し)たい」については、研究者の間でも様々な見解が示されています。置換できる場合と置換できない場合があり、そのメカニズムは実はとても複雑なのです。
文芸文化学科では「日本語学研究A」で日本語教育の文法を学びます。日本語に関心のある方、ぜひ一緒に学んでみませんか。
「海がみたい 人を愛したい 怪獣にも 心があるのさ」
このフレーズでは、怪獣がしたいことが2つ挙げられています。砂漠に住む怪獣の願いは、海を見ることと、人を愛すこと。そう、海を見ること……。実は、「海がみたい」は、「海をみたい」と言い換えることができます。
砂漠にいる怪獣だからこそ「見たいもの」と言えば「海」なのでしょう。ここでの「が」には、「他のものではなく、海こそが見たいものなんだ」という意味、つまり、排他の意味を感じとることができます。
「~が(し)たい」と「~を(し)たい」については、研究者の間でも様々な見解が示されています。置換できる場合と置換できない場合があり、そのメカニズムは実はとても複雑なのです。
文芸文化学科では「日本語学研究A」で日本語教育の文法を学びます。日本語に関心のある方、ぜひ一緒に学んでみませんか。

夜を駆けたり、夜に駆けたり―スピッツ『夜を駆ける』・YOASOBI『夜に駆ける』
『夜に駆ける』は2019年にリリースされたYOASOBIの楽曲です。今の学生にとっては「駆ける」といえば「夜に」なのでしょうが、遡ること17年前、スピッツが『夜を駆ける』という楽曲をリリースしています。
では、「に」と「を」の違いにより、どんなニュアンスが生まれるのでしょうか。
では、「に」と「を」の違いにより、どんなニュアンスが生まれるのでしょうか。
スピッツ『夜を駆ける』(2002年)
「君と遊ぶ 誰もいない市街地 目と目が合うたび笑う 夜を駆けていく 今は撃たないで 遠くの灯りの方へ 駆けていく」
もともと「夜」は時間に関わる語です。しかし、空間的な経過域を表す「を」格を使用することで、闇に包まれた空間を「駆ける」ことがイメージされます。ちなみに、楽曲中では「遠くの灯りの方へ」と方向が示され、暗がりのなか、ほのかに見える灯りを目指し、僕と君が移動している情景をイメージすることができます。
では「夜に駆ける」の場合はどうでしょうか。
もともと「夜」は時間に関わる語です。しかし、空間的な経過域を表す「を」格を使用することで、闇に包まれた空間を「駆ける」ことがイメージされます。ちなみに、楽曲中では「遠くの灯りの方へ」と方向が示され、暗がりのなか、ほのかに見える灯りを目指し、僕と君が移動している情景をイメージすることができます。
では「夜に駆ける」の場合はどうでしょうか。

YOASOBI「夜に駆ける」(2019年)
「忘れてしまいたくて閉じ込めた日々に 差し伸べてくれた君の手を取る 涼しい風が空を泳ぐように今吹き抜けていく 繋いだ手を離さないでよ 二人今、夜に駆け出していく」
タイトル「夜に駆ける」に関連するフレーズは最後に登場します。「(夜に)駆け出していく」という表現は、開始という意味を添える「~だす(出す)」を伴って、その空間に向かって移動する、というイメージを伝えます。ここでは、移動先、つまり着点が「に」で表されているわけです。
YOASOBIの「夜に駆ける」は、ある短編小説が原作となっています。その小説も「夜空に向かって駆けだした」というフレーズで終わります。
なぜ、YOASOBIの「夜に駆ける」に用いられる格助詞は「に」なのか。「夜」が象徴しているものは何か。疾走感あふれるポップなメロディーに隠されたメッセージとは……。
YOASOBIの楽曲は、原作小説を知ったうえで改めて聴くと、違った世界観を体感することができます。
タイトル「夜に駆ける」に関連するフレーズは最後に登場します。「(夜に)駆け出していく」という表現は、開始という意味を添える「~だす(出す)」を伴って、その空間に向かって移動する、というイメージを伝えます。ここでは、移動先、つまり着点が「に」で表されているわけです。
YOASOBIの「夜に駆ける」は、ある短編小説が原作となっています。その小説も「夜空に向かって駆けだした」というフレーズで終わります。
なぜ、YOASOBIの「夜に駆ける」に用いられる格助詞は「に」なのか。「夜」が象徴しているものは何か。疾走感あふれるポップなメロディーに隠されたメッセージとは……。
YOASOBIの楽曲は、原作小説を知ったうえで改めて聴くと、違った世界観を体感することができます。

格助詞が伝える切ない気持ち―浜崎あゆみ『LOVE~destiny~』
90年代の終わり、日本の音楽シーンに颯爽と登場した浜崎あゆみさん。「女子高生のカリスマ」と呼ばれた彼女は、ティーンエイジャーにとって憧れの存在でした。
そんな彼女は、デビュー当時からほぼすべての楽曲を自分で作詞しています。今回、注目する楽曲は、別れた恋人に対する切ない恋心を綴った楽曲です。
そんな彼女は、デビュー当時からほぼすべての楽曲を自分で作詞しています。今回、注目する楽曲は、別れた恋人に対する切ない恋心を綴った楽曲です。
浜崎あゆみ『LOVE~Destiny~』(2001)
【1番サビ】
「ただ出会えたことに ただ愛したことに 想い合えなくても La La La La... 忘れない」
【2番サビ】
「ただ出会えたことで ただ愛したことで 想い合えたことで これからも...」
【最後のサビ】
「ただ出会えたことを ただ愛したことを 2度と会えなくても La La La La... 忘れない」
「ただ出会えたこと」および「ただ愛したこと」に後続する格助詞は、それぞれ「に」「で」「を」の3通りです。ここで、「出会えたこと」と「愛したこと」につながる述語部分に注目してみると、1番と3番では、「忘れない」と述語が示されていますが、2番では、フレーズを受ける述語が省略されていることに気づきます。
続いて、サビの文構造を確認してみましょう。3番は「ただ出会えたことを ただ愛したことを」→「忘れない」とつながりが自然ですが、1番は「ただ出会えたことに ただ愛したことに」→「忘れない」とそのつながりに、文法的な違和感を抱きます。
では、1番の歌詞はどのように解釈すればよいのでしょうか。サビの少し前に、以下のようなフレーズがあります。
「ふたりで過ごした日々は ウソじゃなかったこと 誰より誇れる」
格助詞「に」の用法を考慮しながら、「忘れない」に至るまでの感情を考えると、「出会えたことに感謝している」「愛したことに誇りを持っている」というような、終わった恋を前向きに捉えようとする切ない想いを推察することができます。歌詞に描かれていない感情の推察にあたって、格助詞「に」を手がかりにすることができるのです。
また、述語が省略されている2番については、サビにある「これからも」と、サビ直後の「真実と現実の全てから目を反らさずに 生きて行く証にすればいい」という歌詞から、「生きて行く」という強い決意を想定することができます。ちなみに、2番のサビに用いられている格助詞「で」からは、それを拠り所にしていく、という「手段・方法」の意味を読み取ることができるでしょう。
そして、ラストのサビは、「ただ出会えたことを ただ愛したことを」→「忘れない」と素直な気持ちが、優しく丁寧に歌われます。
このように、格助詞を手がかりに、私たちは省略された述語部分を補うことができます。ことばを費やさず、スローペースでしっとりと聴かせるバラードだからこそ、格助詞の使用に工夫があるのです。
「ただ出会えたことに ただ愛したことに 想い合えなくても La La La La... 忘れない」
【2番サビ】
「ただ出会えたことで ただ愛したことで 想い合えたことで これからも...」
【最後のサビ】
「ただ出会えたことを ただ愛したことを 2度と会えなくても La La La La... 忘れない」
「ただ出会えたこと」および「ただ愛したこと」に後続する格助詞は、それぞれ「に」「で」「を」の3通りです。ここで、「出会えたこと」と「愛したこと」につながる述語部分に注目してみると、1番と3番では、「忘れない」と述語が示されていますが、2番では、フレーズを受ける述語が省略されていることに気づきます。
続いて、サビの文構造を確認してみましょう。3番は「ただ出会えたことを ただ愛したことを」→「忘れない」とつながりが自然ですが、1番は「ただ出会えたことに ただ愛したことに」→「忘れない」とそのつながりに、文法的な違和感を抱きます。
では、1番の歌詞はどのように解釈すればよいのでしょうか。サビの少し前に、以下のようなフレーズがあります。
「ふたりで過ごした日々は ウソじゃなかったこと 誰より誇れる」
格助詞「に」の用法を考慮しながら、「忘れない」に至るまでの感情を考えると、「出会えたことに感謝している」「愛したことに誇りを持っている」というような、終わった恋を前向きに捉えようとする切ない想いを推察することができます。歌詞に描かれていない感情の推察にあたって、格助詞「に」を手がかりにすることができるのです。
また、述語が省略されている2番については、サビにある「これからも」と、サビ直後の「真実と現実の全てから目を反らさずに 生きて行く証にすればいい」という歌詞から、「生きて行く」という強い決意を想定することができます。ちなみに、2番のサビに用いられている格助詞「で」からは、それを拠り所にしていく、という「手段・方法」の意味を読み取ることができるでしょう。
そして、ラストのサビは、「ただ出会えたことを ただ愛したことを」→「忘れない」と素直な気持ちが、優しく丁寧に歌われます。
このように、格助詞を手がかりに、私たちは省略された述語部分を補うことができます。ことばを費やさず、スローペースでしっとりと聴かせるバラードだからこそ、格助詞の使用に工夫があるのです。

トップアイドルの歌詞を読み解く―白石麻衣『じゃあね』
坂道グループの歌詞は、基本的にはプロデューサーの秋元康氏が手がけています。そんな坂道グループにおいて、秋元康氏以外による作詞は、白石麻衣さんが初めてでした。白石麻衣さんといえば、乃木坂46の1期生で、乃木坂46をけん引したメンバー。彼女の卒業シングルに収録されたソロ曲「じゃあね。」に、格助詞の使用をみてみましょう。
白石麻衣『じゃあね。』(2020)
『じゃあね。』には、乃木坂46で過ごした8年間の歩みが描かれています。グループに所属するアイドルにとって「卒業」を決めるタイミングは難しいもの。
「坂道の途中で迷ってた 時に訪れたさよなら “いつかは”と思ったって 口には出せなくって」
という歌詞には、同期の1期生を送り出しながらも、自分の卒業に思いを巡らす彼女の姿を想像することができます。
ここで、1番のサビと最後のサビを比較してみましょう。
【1番サビ】
「もうそろそろ行かなくちゃ 描きかけていた絵に色をつけて 泣いてないって 坂の途中で さよならとありがと。」
【最後のサビ】
「もうそろそろ行かなくちゃ 描きかけていた絵が好きだから 泣いてないで 坂を登って ただ、らしく 歩こう さよならをありがとう。」
1番では、卒業するメンバーに向けて、涙をこらえて、別れと感謝を伝えた白石さんが描かれています。「さよなら」も「ありがと。」も白石さんから卒業するメンバーに向けられています。用いられている格助詞は並列の意味を表す「と」です。
一方、最後のサビでは、送り出される側になった白石さんの心情が描かれることになります。トップアイドルとして過ごした8年間。「もうそろそろ行かなくちゃ」と旅立ちを伝える彼女に、メンバーやファンは万感の思いで「さよなら」を告げたことでしょう。それに対し、彼女が心から「ありがとう。」を伝える構図になっています。対象を表す「を」がそれを表します。
ちなみに、「と」も「を」も母音は「お」。メロディに乗せると母音の響きは一緒。白石さんの異なる立場(送る側・送られる側)を「と」と「を」を使い分けることで表しています。
ついでに、「ありがと。」と「ありがとう。」の違いにも注目したいところです。メンバーへの感謝は、「ありがと。」と、近しい間柄だからこその砕けた表現で、そして、彼女のファンや彼女を支えたすべての人への感謝は、「ありがとう。」と丁寧に。同じメロディで歌われるため、「ありがと。」と「ありがとう。」の違いは感じられませんが、細かいところに白石さんの思い入れが感じられます。
トップアイドルがつむぐ歌詞は、日本語学の観点からも興味深いものでした。
「坂道の途中で迷ってた 時に訪れたさよなら “いつかは”と思ったって 口には出せなくって」
という歌詞には、同期の1期生を送り出しながらも、自分の卒業に思いを巡らす彼女の姿を想像することができます。
ここで、1番のサビと最後のサビを比較してみましょう。
【1番サビ】
「もうそろそろ行かなくちゃ 描きかけていた絵に色をつけて 泣いてないって 坂の途中で さよならとありがと。」
【最後のサビ】
「もうそろそろ行かなくちゃ 描きかけていた絵が好きだから 泣いてないで 坂を登って ただ、らしく 歩こう さよならをありがとう。」
1番では、卒業するメンバーに向けて、涙をこらえて、別れと感謝を伝えた白石さんが描かれています。「さよなら」も「ありがと。」も白石さんから卒業するメンバーに向けられています。用いられている格助詞は並列の意味を表す「と」です。
一方、最後のサビでは、送り出される側になった白石さんの心情が描かれることになります。トップアイドルとして過ごした8年間。「もうそろそろ行かなくちゃ」と旅立ちを伝える彼女に、メンバーやファンは万感の思いで「さよなら」を告げたことでしょう。それに対し、彼女が心から「ありがとう。」を伝える構図になっています。対象を表す「を」がそれを表します。
ちなみに、「と」も「を」も母音は「お」。メロディに乗せると母音の響きは一緒。白石さんの異なる立場(送る側・送られる側)を「と」と「を」を使い分けることで表しています。
ついでに、「ありがと。」と「ありがとう。」の違いにも注目したいところです。メンバーへの感謝は、「ありがと。」と、近しい間柄だからこその砕けた表現で、そして、彼女のファンや彼女を支えたすべての人への感謝は、「ありがとう。」と丁寧に。同じメロディで歌われるため、「ありがと。」と「ありがとう。」の違いは感じられませんが、細かいところに白石さんの思い入れが感じられます。
トップアイドルがつむぐ歌詞は、日本語学の観点からも興味深いものでした。

「恋をする」のは誰に?誰と?―平井堅『僕は君に恋をする』
今回は格助詞を取り上げます。格助詞とは、おもに名詞に付いて、その体言と他の語との意味関係を示す助詞です。今回は格助詞の使い方が秀逸な楽曲を紹介します。
平井堅『僕は君に恋をする』(2009)
映画『僕の初恋をキミに捧ぐ』の主題歌です。「僕は君に恋をする」というフレーズが聞かせどころ、いわゆるサビに登場します。
1度目は「僕は君に恋をする」ですが、2度目は「僕は君と恋をする」です。メロディが同じだからこそ、「に」と「と」の違いが印象的に響きます。「僕は君に恋をする」では、格助詞「に」を用いることで、「僕」の思いが「君」に向けられていることがわかります。ただ、「君」の思いはこの段階では描写されていません。
一方、「僕は君と恋をする」では、「僕」の思いが「君」に届き、両想いになったことがうかがえます。対等の関係であることを「と」が示しているのです。
格助詞が「僕」と「君」の関係性の変化を伝えている作品です。
1度目は「僕は君に恋をする」ですが、2度目は「僕は君と恋をする」です。メロディが同じだからこそ、「に」と「と」の違いが印象的に響きます。「僕は君に恋をする」では、格助詞「に」を用いることで、「僕」の思いが「君」に向けられていることがわかります。ただ、「君」の思いはこの段階では描写されていません。
一方、「僕は君と恋をする」では、「僕」の思いが「君」に届き、両想いになったことがうかがえます。対等の関係であることを「と」が示しているのです。
格助詞が「僕」と「君」の関係性の変化を伝えている作品です。

「俺たちの合言葉」に意味はある?―乃木坂46『ジャンピングジョーカーフラッシュ』
多趣味な文芸文化学科の学生たち。アイドル好きも多くいます。授業では、乃木坂46をはじめとする坂道シリーズの楽曲も取り上げます。今回は乃木坂46の楽曲に格助詞の使用をみてみましょう。
乃木坂46『ジャンピングジョーカーフラッシュ』(2022)
乃木坂46の4期生楽曲です。乃木坂46の楽曲の中でも特にアップテンポでロック調のナンバーです。ちなみに、タイトル『ジャンピングジョーカーフラッシュ』は、The Rolling Stonesの楽曲『Jumpin' Jack Flash』のオマージュです。そのため『ジャンピングジョーカーフラッシュ』の中では、「誰かが昔 歌ったんだってね?」「流行った歌にもあったんだろう?」のように『Jumpin' Jack Flash』を意識したフレーズがみられます。
では、「ジャンピングジョーカーフラッシュ」とはどのような意味なのでしょうか。「語呂良けりゃいいんだ」「俺たちの合言葉」と強調されている「ジャンピングジョーカーフラッシュ」。つまり、語そのものは、さほどの意味をもたないことがわかります。そのあたりも『Jumpin' Jack Flash』に通ずるものがあります。
意味をもたないからこそ、後続する表現も自由。以下のフレーズは全て同じメロディで歌われます。
「ジャンピングジョーカーフラッシュでGO!GO!」
「ジャンピングジョーカーフラッシュが最高!」
「ジャンピングジョーカーフラッシュでCome on!」
「ジャンピングジョーカーフラッシュは最強!」
「ジャンピングジョーカーフラッシュでKnock Knock」
「ジャンピングジョーカーフラッシュをOpen」
使用されている格助詞は「で」「が」「を」です(「は」は格助詞ではありません)。「最高」で「最強」で「Open」することもできる「ジャンピングジョーカーフラッシュ」……。どんな意味かを考えたいところですが、メンバーは「難しく考えないでくれ」と歌っていますので、この曲を聴く時は、ハイテンションでロックなナンバーを純粋に楽しむのが良さそうですね。