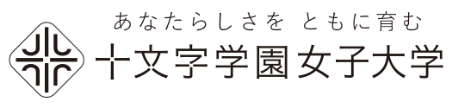若桐ダイアリー
若桐会事務局スタッフによる日々の記録です。
※写真掲載に関して肖像権等の不都合があった場合、即刻削除いたしますのでご連絡ください。
※写真掲載に関して肖像権等の不都合があった場合、即刻削除いたしますのでご連絡ください。
子育て講演会「はらっぱ」におじゃましました!
若桐ダイアリーでは、2020年から「はらっぱ」におじゃまさせていただき、その時の様子を若桐ダイアリーで紹介しております。

子育て講座「はらっぱ」は、十文字学園女子大学と十文字女子大附属幼稚園の共同開催となっており、附属幼稚園に大学から先生をお迎えして、附属幼稚園の保護者の方や地域の皆さんを対象に専門家のお話を聞ける講座となっております。
参加費は無料。
現地参加とオンラインの同時開催です!
参加費は無料。
現地参加とオンラインの同時開催です!
2020年度
| 第1回 | 10月 2日 | 幼児教育学科 | 名達英詔先生 | 「子どものコトづくりと経験」 | 記事はこちら |
| 第2回 | 11月 6日 | 健康栄養学科 | 小長井ちづる先生 | 「子どもの食を守るための正しい情報選択とは?」 | 記事はこちら |
| 第3回 | 1月22日 | 十文字女子大附属幼稚園 園長 | 伊集院理子先生 | 「根を育てる生活 ~幼児期に大切にしたいこと~」 | 記事はこちら |
2021年度
| 第1回 | 7月 9日 | 健康栄養学科 | 徳野裕子先生 | 「感染症に打ち勝つ体つくりに必要な食育」 | 記事はこちら |
| 第2回 | 9月24日 | 十文字女子大附属幼稚園 園長 | 伊集院理子先生 | 「根を育てる生活~幼児期に大切にしたいこと~PartⅡ」 | 記事はこちら |
| 第3回 | 11月24日 | 幼児教育学科 | 大宮 明子先生 | 「バイリンガル教育 ~海外の事例から見えること~」 | 記事はこちら |
| 第4回 | 1月26日 | 幼児教育学科 | 金允貞先生 | 「自己主張のはじまり-自立への一歩」 | 記事はこちら |
2022年度
| 第1回 |
7月8日 | 十文字女子大附属幼稚園 園長 |
伊集院理子先生 | 「根を育てる生活~幼児期に大切にしたいこと~PartⅢ」 | 記事はこちら |
| 第2回 | 9月20日 | 十文字学園女子大学 副学長 |
安達一寿先生 | 「子ども達の発達・成長とICT活用のこれから」 | 記事はこちら |
| 第3回 | 11月25日 | 人間福祉学科 | 亀﨑美沙子先生 | 「VUCA時代の子どもの育ちと子育て」 | 記事はこちら |
| 第4回 | 1月25日 | 幼児教育学科 | 水島ゆめ先生 | 「素材との触れ合い〜豊かな感性を育む〜」 | 記事はこちら |
2023年度
「はらっぱ」へのご参加
十文字女子大附属幼稚園の園庭
バックナンバー
過去の記事は下記よりご覧いただけます。